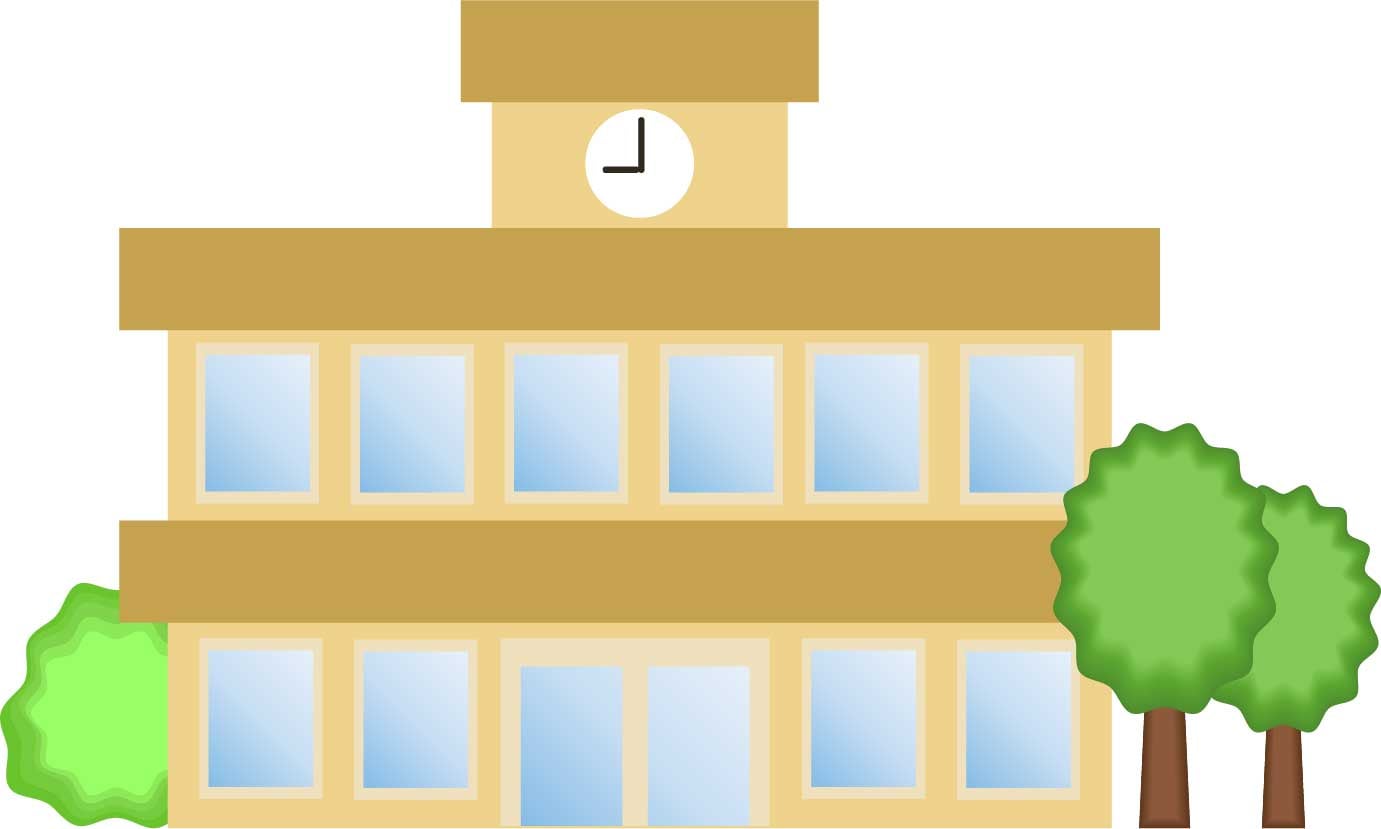不登校に対しては様々な取り組みが行われていますが、依然として子どもたちにかかわる大きな問題になっています。
不登校の児童生徒に適切な対応できるように、文部科学省では、不登校の判断の目安になる定義を示しています。
不登校の正しい定義とその内容、特に多いとされている2つの原因とその対応策についてまとめました。
目次
文部科学省が判断のめやすとしている不登校の定義とは?
文部科学省は、不登校を次のように定義しています。
不登校の定義
学校を連続又は断続して年間30日以上欠席していて、
何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的要因・背景により、子どもが登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるもの。
ただし、病気や経済的理由によるものを除く。
「何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的要因・背景」とは?
いじめなどの人間関係や学業不振などの学校生活に原因があるもの、家庭不和や虐待といった家庭環境に原因があるもの、非行などがあげられます。
また、情緒の混乱や無気力といった本人に起因するものがあり、原因がひとつということは少なく、多くはいくつかの原因が複合しています。
不登校に多い2つの原因と原因別の家庭での対応策とは
文部科学省は、不登校をその原因別に分類していますが、その中では次の2つの原因が特に多くなっています。
不安などの情緒混乱型
不登校の原因として一番多く、学校に行くことに強い不安感がありますが、行かないことへの罪悪感にも苦しめられています。
情緒不安定で気分の変動が大きく、頭痛や腹痛といった身体症状を訴えることも多いのが特徴です。
このタイプの不登校は無理に学校へ行かせるのは逆効果で、学校を休んで休養させ、家庭であたたかく見守ることで、落ち着きや心の元気を取り戻します。
無気力型
本人にもはっきりとした原因が分からないまま、「なんとなく行きたくない」というように、無気力になって学校へ行けなくなるタイプです。
学校へ行きたいという気持ちがあまりなく、行かないことへの罪悪感も少なく、感情の起伏もあまり見られません。
登校を促したり、友達が迎えに来ると学校へ行けることがありますが長続きせず、親や教師が根気よく働きかける必要があります。
文部科学省が定める不登校の定義と2つの原因別対応策まとめ
・文部科学省の不登校の定義
学校を連続又は断続して年間30日以上欠席していて、
何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的要因・背景により、子どもが登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるもの。
ただし、病気や経済的理由によるものを除く。
・「何らかの心理的・情緒的・身体的あるいは社会的要因・背景」とは?
人間関係や学業不振などの学校生活、家庭不和や虐待といった家庭環境、非行、情緒の混乱や無気力といった本人に起因するものなど。
・不登校に多い2つの原因と対応策
不安などの情緒混乱型の場合
・不登校の原因として一番多く、学校に行くことに強い不安感があるが、行かないことへの罪悪感にも苦しめられている。
・情緒不安定で気分の変動が大きく、頭痛や腹痛といった身体症状を訴えることが多い。
・無理に学校へ行かせるのは逆効果で、学校を休んで休養させ、家庭であたたかく見守ることで、落ち着きや心の元気を取り戻す。
無気力型の場合
・本人にもはっきりとした原因が分からないまま、「なんとなく行きたくない」というように、無気力になって学校へ行けなくなるタイプ。
・学校へ行きたいという気持ちがあまりなく、行かないことへの罪悪感も少なく、感情の起伏もあまり見られない。
・登校を促したり、友達が迎えに来ると学校へ行けることがありますが長続きせず、親や教師が根気よく働きかける必要がある。