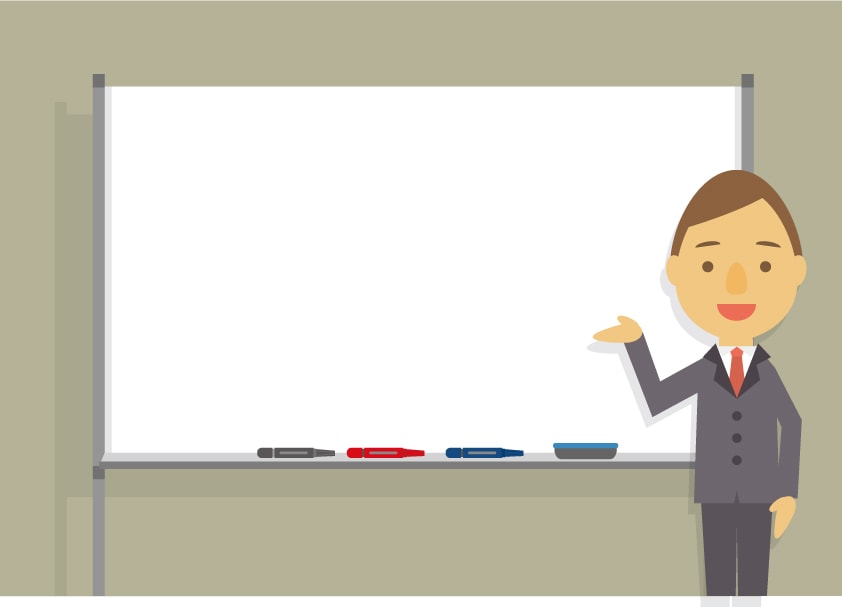学校に行っていない児童や生徒の「不登校」には、それぞれに心理的、情緒的、身体的などに、さまざまな状況や背景の影響で年間30日以上登校していない状態と言われています。
一言に不登校といっても、その児童や生徒によって原因も理由もそれぞれに違いがありますが、文部科学省や秋田県総合教育センターなどが調査結果に基づいて、7つのタイプへの分類を試みています。
文部科学省などの専門機関が調査結果によって分類した不登校にみられる7つのタイプを紹介します。
不登校にみられる7つのタイプとは?
不登校は、文部科学省や秋田県総合教育センターなどによって、次のような7つのタイプに分類されています。
1.学校生活が原因となった不登校
2.遊びや非行グループに入ったりすることで登校しない不登校
3.何事にも無気力で、登校することに義務感を感じず、なんとなく登校しない不登校
4.登校の意思はあるものの、漠然とした不安から体の不調を訴える不登校
5.学校に行くことを意図的に拒否する不登校
6.不登校が継続したことで理由が複合し、主たる理由が分からなくなった不登校
7.前述したタイプに分類できない不登校
不登校の7つに分類されたタイプの原因や特徴は?
不登校の状態には、大きく学校での生活に関わるなかで生じた原因、児童や生徒の持つパーソナリティに起因した原因、家庭環境や周囲の友人などとの人間関係による原因などがみられます。
学校の中に不登校の原因がある場合には、勉強の遅れやいじめ被害といったことが多くみられ、学校や家庭での教育支援が必須となり、障害を持っている児童や生徒の場合には専門家の助言やフォローも必要とします。
また、いじめや嫌がらせで不登校となった場合には、本人だけでの解決が難しい場合も多く、両親と教員の共同した分析と対応が求められます。
不登校となる年齢があがるにつれ、学校に対する考え方や子供自身の自尊心や自己肯定感の乏しさなどで、ある意味確固たる信念を持って登校を拒否する場合もあり、本人の意思を良く聞き、対応もそれによって変える必要があります。
7つのタイプに分類される不登校の状態のいずれの場合にも、それぞれの児童や生徒にさまざまな思いや原因が秘められていることが多く、教員や両親が理由や原因を言葉として聞き出してあげるか、言葉にできずに訴えようとしている内容を引き出してあげることが最も重要です。
不登校の7つのタイプと周囲に求められる多様な対応
年々増加傾向にある不登校の児童や生徒の人数ですが、文科省などでは7つのタイプに分類を試み、教員や両親などの対応方法などを模索しています。
不登校となる児童や生徒が置かれる家庭環境や学校での生活は千差万別で、追い込まれる子供達のパーソナリティもさまざまで、状況の受け止め方にも違いがあります。
そのため、不登校となった児童や生徒への対応には、7つのタイプに分類された分析をもとにした短絡的な対応をするのではなく、それぞれの子供と綿密なコミュニケーションを図りながら、言葉で表現できない本音を引き出してあげることが重要です。